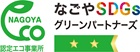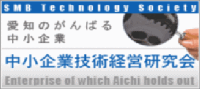プリント基板の組み付け・各種電子機器の組立、電子機器の開発・設計(ハード・ソフト)・製作、多品種少量生産・試作から量産まで対応できます。「エヌケーシステム」にお任せください
〒466-0806 名古屋市昭和区西畑町2番地
技術資料TECHNICAL DOCUMENT
基板べからず集
1.手書き回路図には電源を書くこと
ひどい例として、電源を記入しない回路図で基板を作ったとき、電源がすべて抜けたことがありました。それ以後、手書き回路図で出図のときは必ず電源を記入しています。 ネットリストが生成される回路図入力CAD場合は不要ですが、それでもネットリストは確認してください。
2.回路図には未入力端子処理を書くこと
未入力信号をプルアップまたはプルダウンする場合は、口頭指示や文書だけでなく回路図上にも記載します。さもないとオープンとなるケースが多いです。
3.部品表には形状記号を書くこと
最近は同じICでもいろいろな形状があります。中には同じDIPのICでも225,300mm幅や600mm幅が混在したり、SOP、QFP、PLCCなど様々なバリエーションがあります。
単純にDIPとかSOPと書かずに、カタログ記載の形状番号を正確に示す必要があります。
4.ICのピン配置は時とともにかわる?!
O社のCPU 80C51の44ピンQFPで設計したことがあります。このICのピン配列が途中で変わり、基板を相当数捨てたことがありました。 絶えず最新カタログの入手と部品番号末尾の確認が必要です。
5.SOPとDIPでもピン配列が異なるものもある
同じピン数のSOPとDIP-ICは、たいていは同じですが例外もありますので確認が必要です。
6.配置はインチ・イメージで
部品配置指定のとき、2.54㎜ピッチの部品の間隔を100±0.1㎜などと指定する傾向がありますが、特別の理由がないかぎりは2.54×Nで指示するようにします。
さらに、端子とスルーホール穴は0.4㎜程度の径の差がありますので、部品の配置精度はあまり出ていません。
7.配線指示は一つにまとめる
配線指示を回路図や部品表そのほかの文章で指示することが多いようですが、一つの書類に項目だけでも網羅して、できたらチェックリストを作成して記入してもらいます。
8.基板設計者と喧嘩するな
回路設計者はプライドが高いのか、よく配線条件の緩和を求めた基板設計者と喧嘩しています。 回路特性は当然、回路設計者が理解しているはずで、それに基づいて配線の条件を示したわけです。
しかし基板設計者ははるかに多くの設計図面をみて、多様な回路設計者と接しています。目の肥えた基板設計者は貴重な情報源ですから、仲良くして情報を得ましょう。
9.シルクの間違いは致命的
シルクの部品記号を修正するのを忘れて、間違った部品を部品を実装されたことがあります。
シルクは部品実装の目標にする場合もあり、実装ミスの原因になります。
10.ULマークを忘れた
これはよくあるミスですが、致命的であり、ボードの交換が必要になります。
11.日本の気違いまたメイドさん?
基板設計指示書を書かずに口頭でMADE IN JAPANの記入を頼むとこんなスペルになります。
「MAID IN JAPAN」 「MAD IN JAPAN」
12.基板を固定すること
表面実装部品は基板がたわむと、はんだはがれの危険があります。市場で操作されるスイッチや着脱されるコネクタを直接基板に実装する場合(できたら避けたい)、必ずスイッチやコネクタの部分に基板固定穴を設けましょう。
13.基板の寸法精度に期待するな
一般の基板外形寸法は±0.2㎜程度です。VME基板の基準寸法は±0.15㎜ですので注意してください。本当に必要なら、基板製造会社と調整が必要です。
(ルーター加工なら寸法精度は高いですが、金型、Vカットなどの場所は必ずズレます。)
14.寸法指示は中央値で
基板寸法は中央値で指示しないと指示数値が使用されることが多いので、中央値を使用しましょう。
15.古いフィルムは捨てろ
何年か前の基板を再度生産するため、古い基板を使用する場合がありますが、フィルムは汚れや傷、寸法変化が避けられません。大型の高密度多層板では危険がともないます。思い切ってフィルムを作りなおすことも必要です。
16.DRCを忘れるな
CADにもよりますが、DRC(デザイン・ルール・チェック)には時間がかかります。CADのターミナルが少ない会社では、帰る前にDRCを実行させ翌朝に確認します。納期に追われ変更が少ない場合、DRCを省略してしまうケースが多いようです。一つのエラーでほかのエラーが隠されることもありますので、必ずDRCが正常終了を示すまで行います。
(最近ではPCの処理速度が向上しているので、かなり待ち時間は短くなりました。)
17.基板のショートや断線は常識
高い信頼性が必要な回路設計を行うとき、基板パターンが断線したりショートするのは常識と考えたほうが間違いありません。これが原因で重大なトラブルを起こし、PL訴訟を受けたら負けることになると思いますので注意が必要です。システム上、致命的なトラブルにならないような設計が重要です。
18.パワトラに注意
パワートランジスタは発熱します。放熱版に固定されていると基板にストレスが加わり、ランドがはがれることがあります。また、固定しなければ振動でパターンがはがれます。ストレスの低減、大きめのランドの使用、パターンの引き出しを両面で行います。
19.小径ビヤーはよく切れる
例として基板一枚に500個の小径ビヤーが使用された基板を1000枚部品実装したとき、2個のビヤーのオープンがありました。ビヤーの不良率は1/250000となりますが、製品は、1/500です。 最近はパソコンにも小径ビヤーが多く使用されており、信頼性も高いのでしょうが、回路設計のときは注意が必要です。
20.外部信号に0.15㎜幅パターンを使うな
外部と直接接している信号は、誤結線などで過電流が流れることが多いのです。部品で保護機能を設けてもパターンが焼ければ製品は不良となります。できるだけ太くしたほうが良いでしょう。ほかが燃えるかもしれませんけど。
21.基板耐圧に注意
JISの基準では、電圧とパターンの必要ギャップは500Vで0.76㎜となっています。さらに基準の根拠は不明ですが、内層では耐圧が高いということでギャップを0.3㎜くらいにしている基板メーカーもありました。 これを信じて300Vから400Vの発生する信号のギャップを0.3㎜としてクレームが多発した例があります。 電取法はAC100Vで0.3㎜となっていますので、これを採用します。
22.面取りし過ぎに注意
フィルムには伸び縮みがあります。多面付けを多くしてフィルムサイズが広すぎるとフィルムの周辺のパターンにずれが生じます。
23.パターンをヒューズに使うべからず
パターンの溶断電流に期待して、パターンを故意に細くしてヒューズ代わりに使う設計者が、いまだにいるようです。ヒューズは溶断時間の管理が重要です。プリントパターン によるヒューズでは条件によっては溶断せずに発熱が進み、周辺の半田を溶かしとんでもないことになります。必ずヒューズを使用して溶断時間を測定します。
バナースペース
エヌケーシステム株式会社
〒466-0806
名古屋市昭和区西畑町2番地